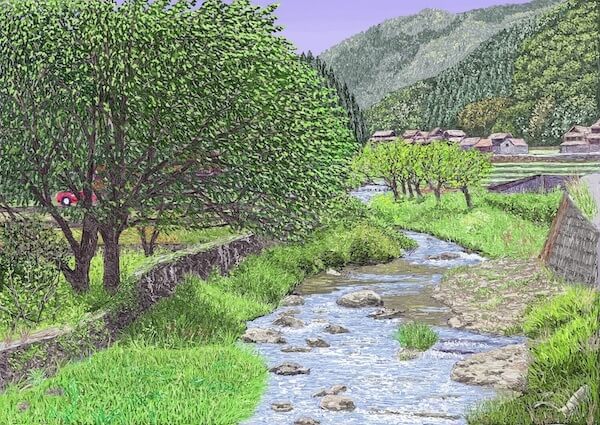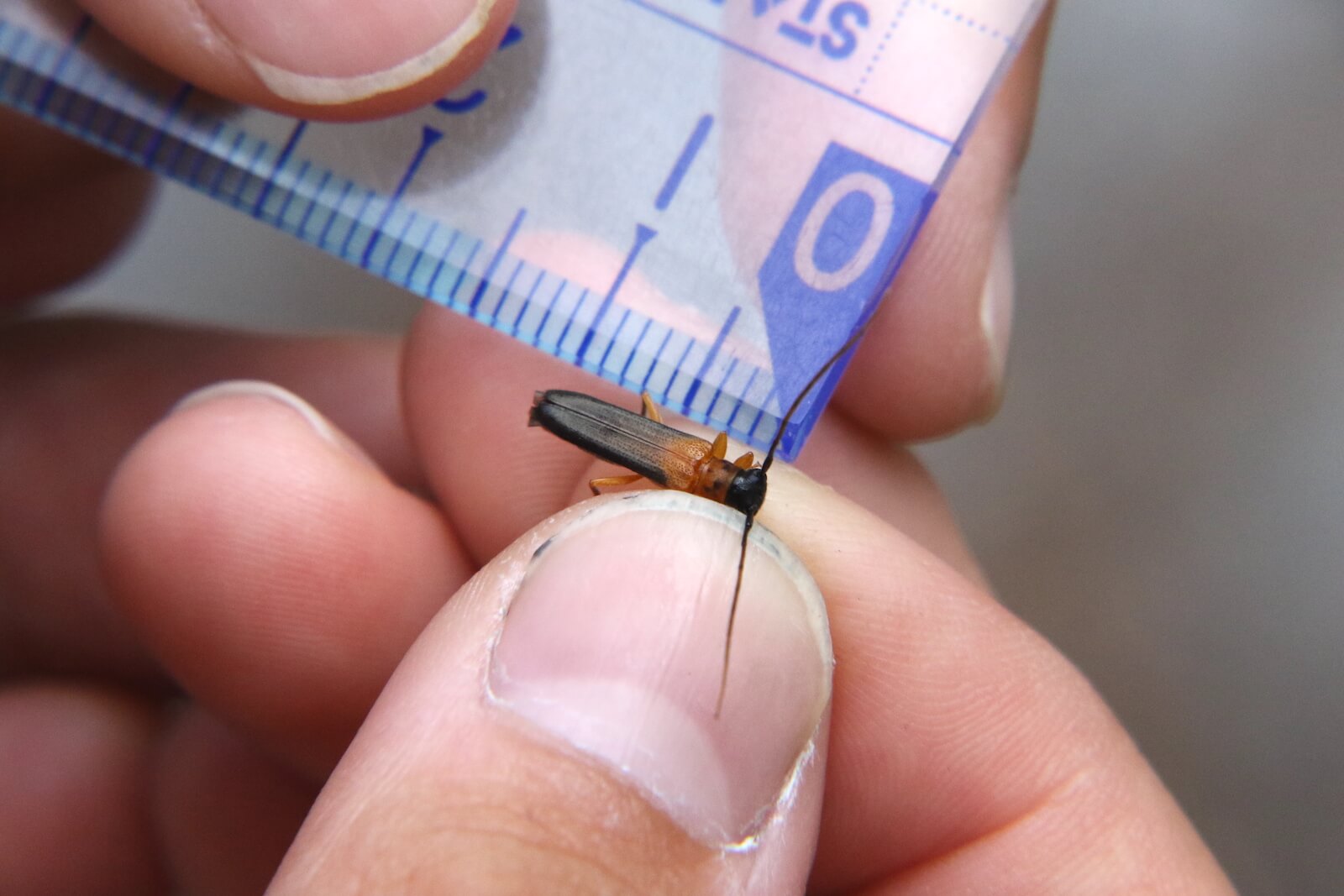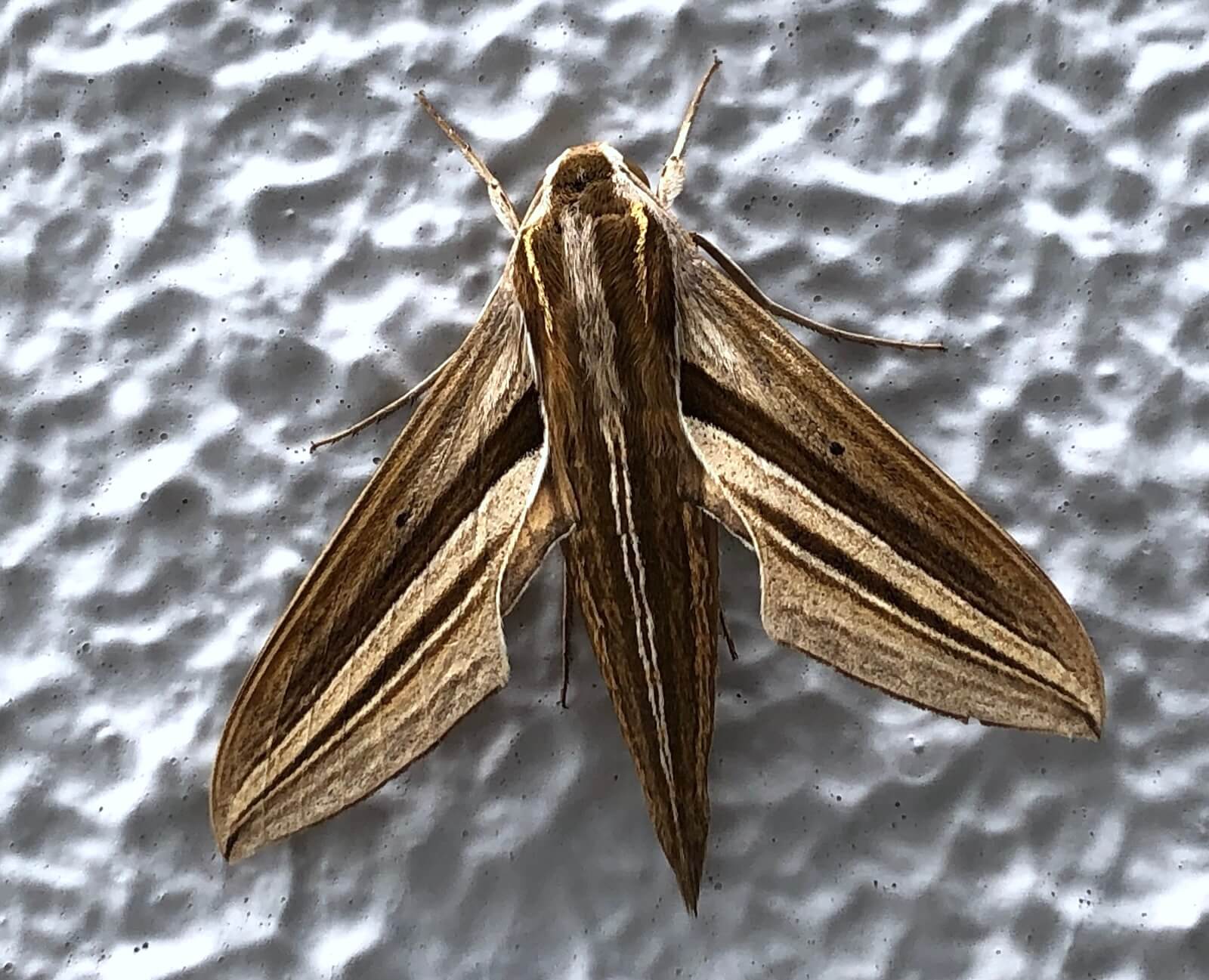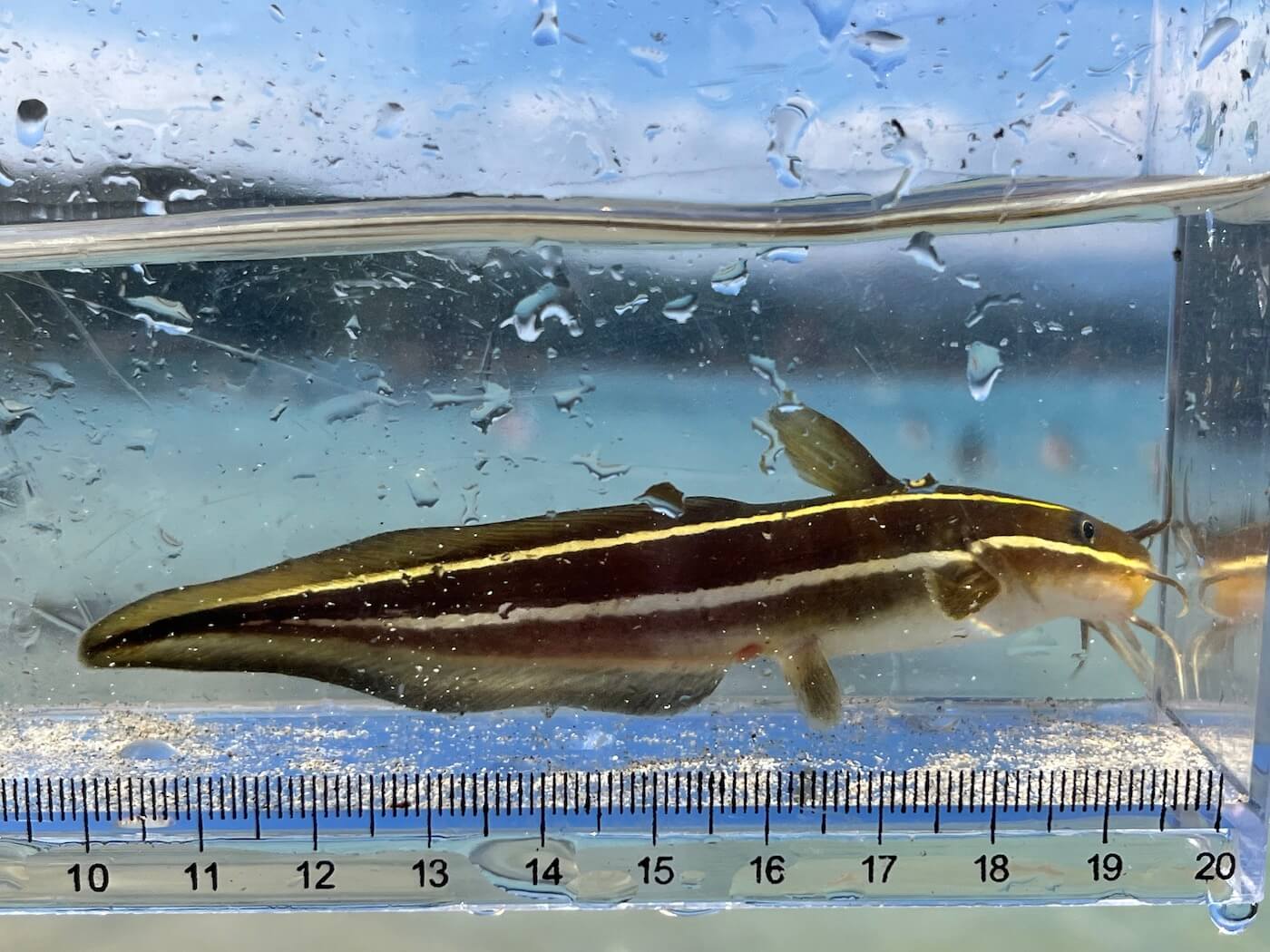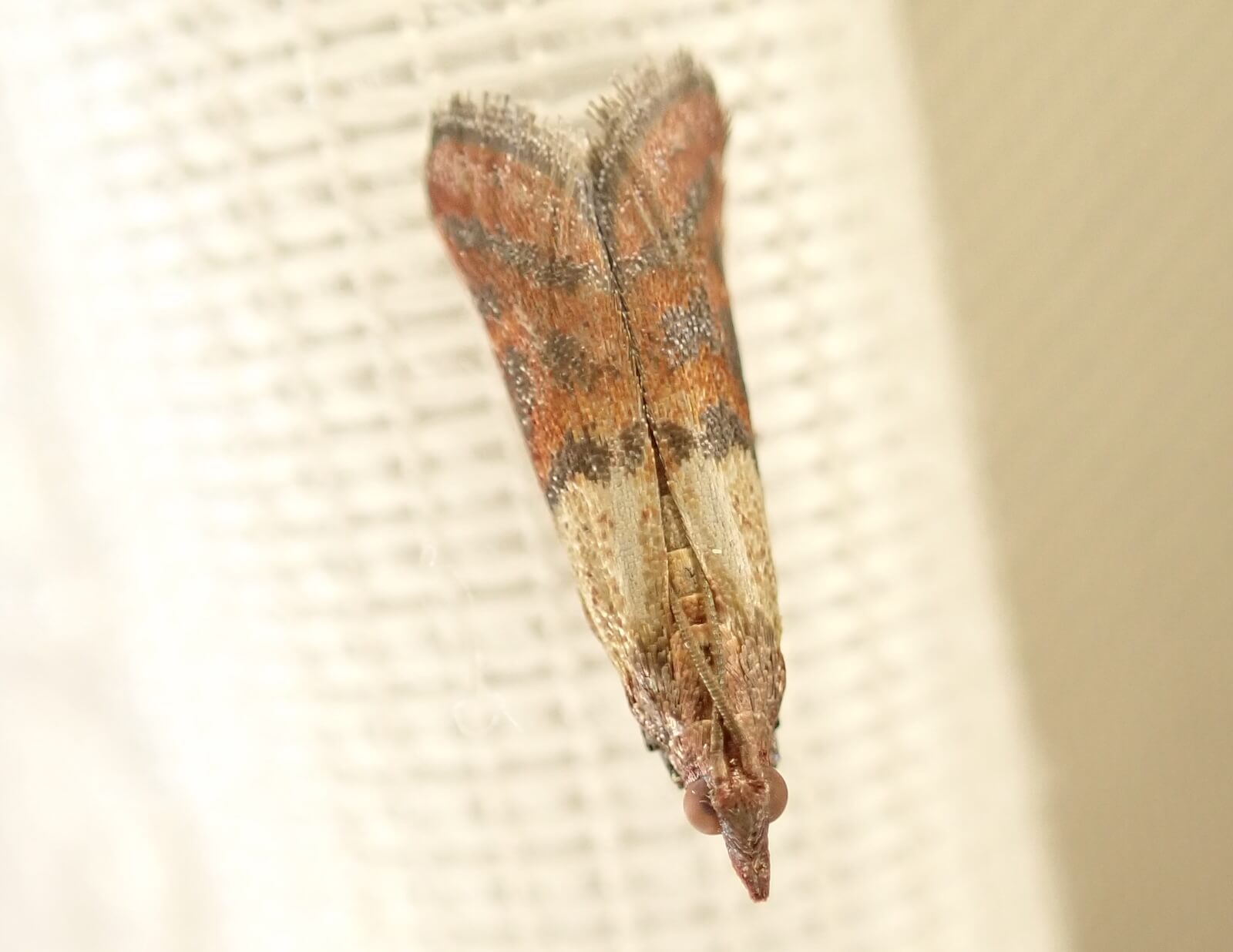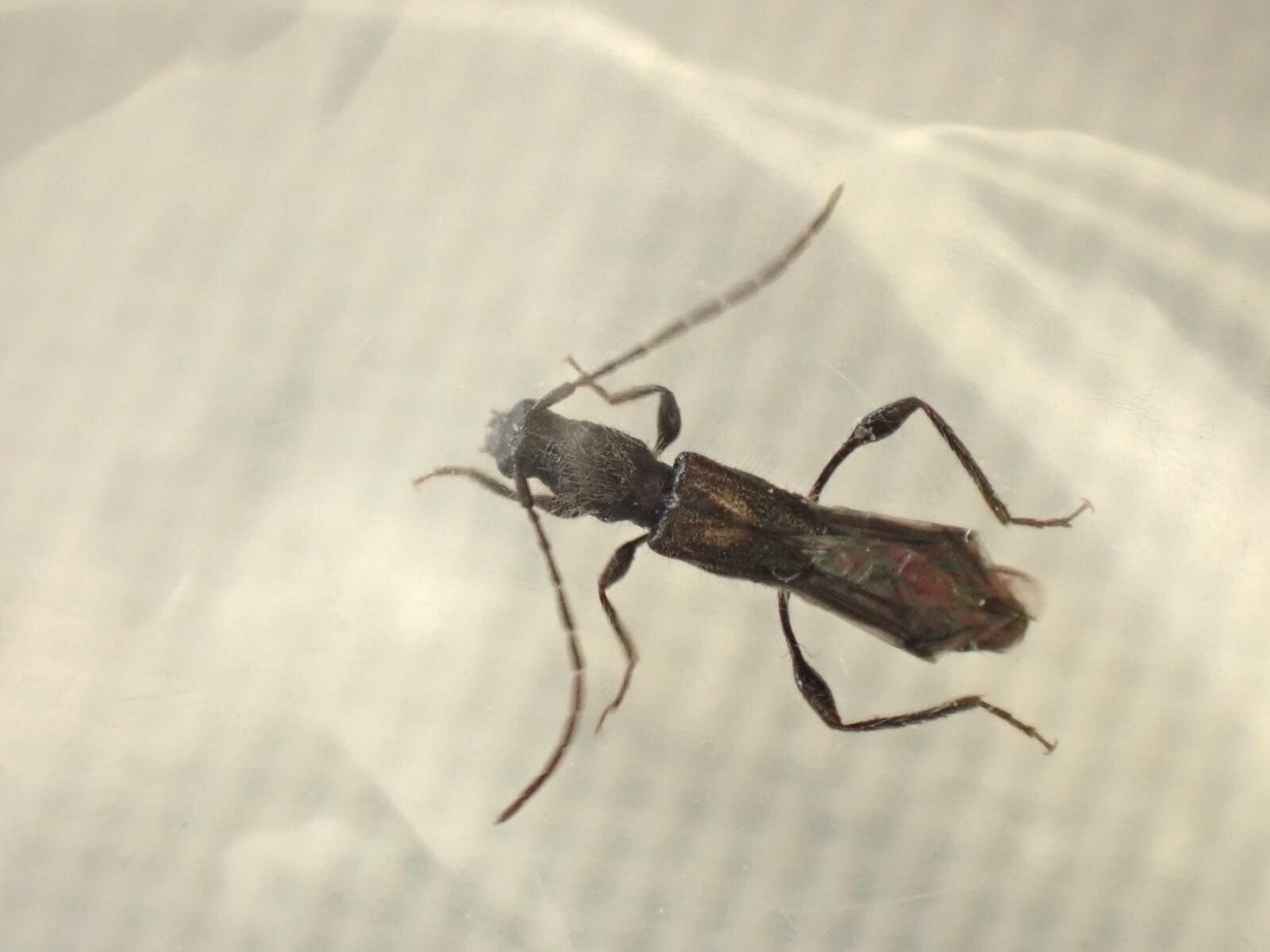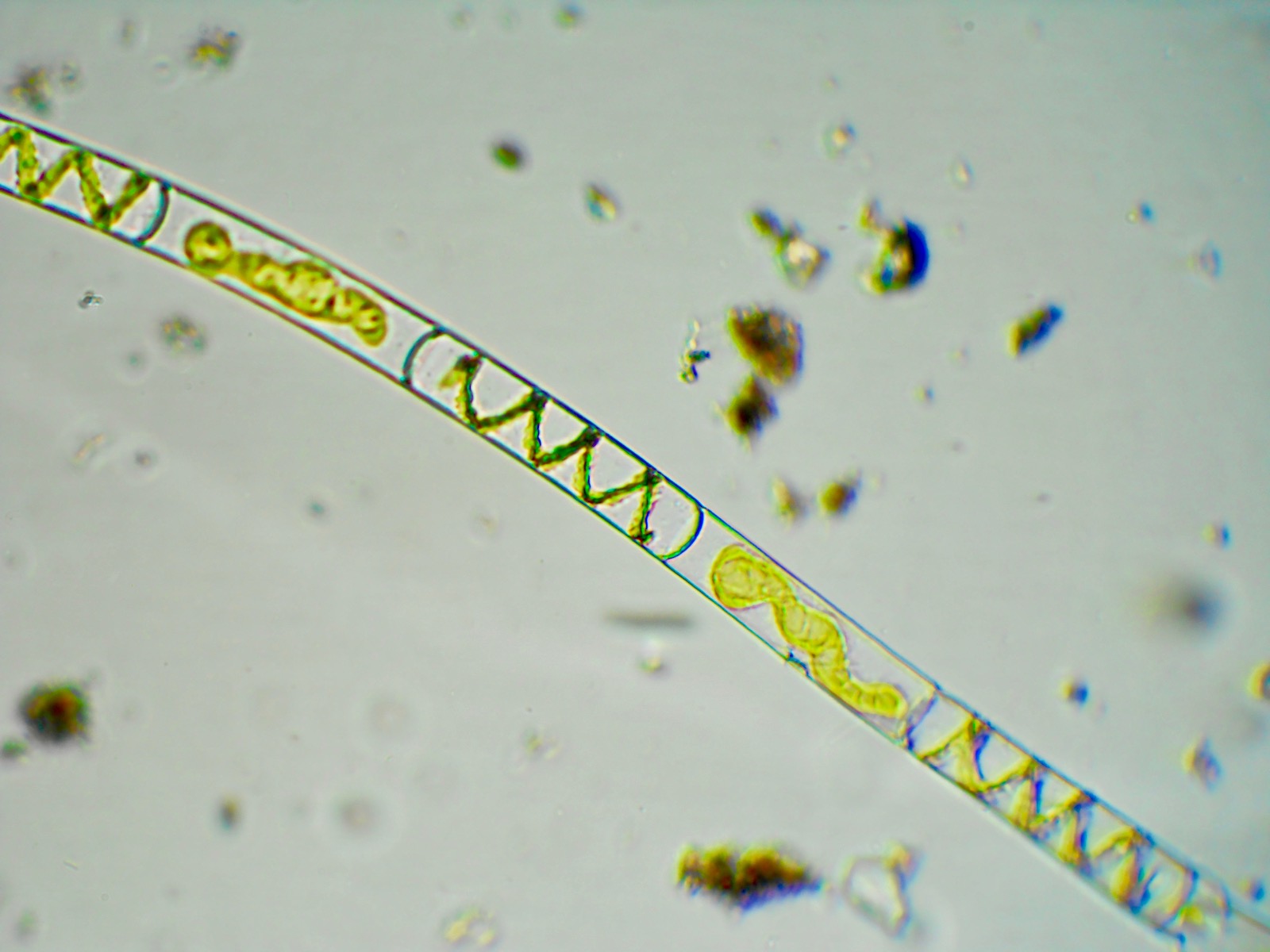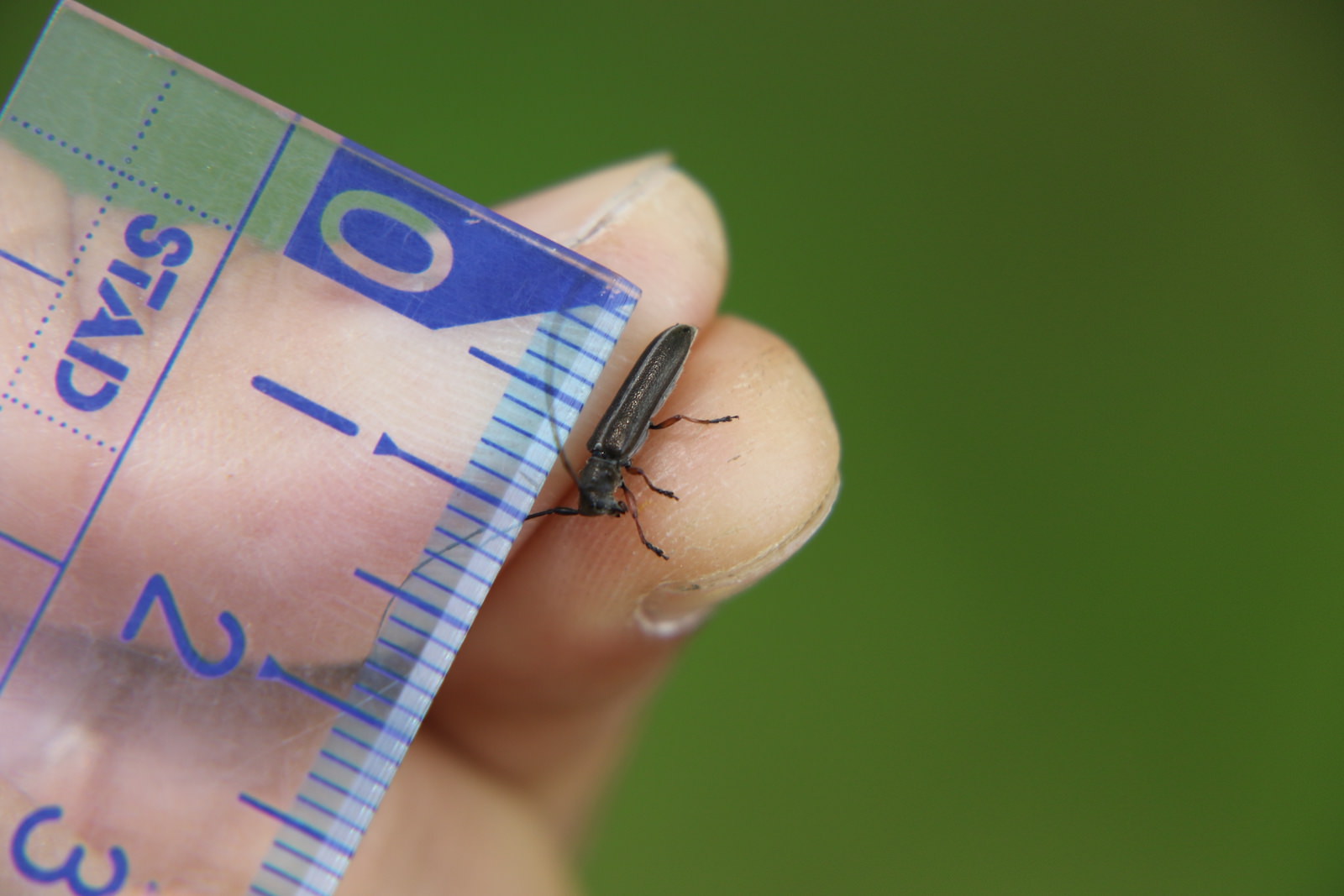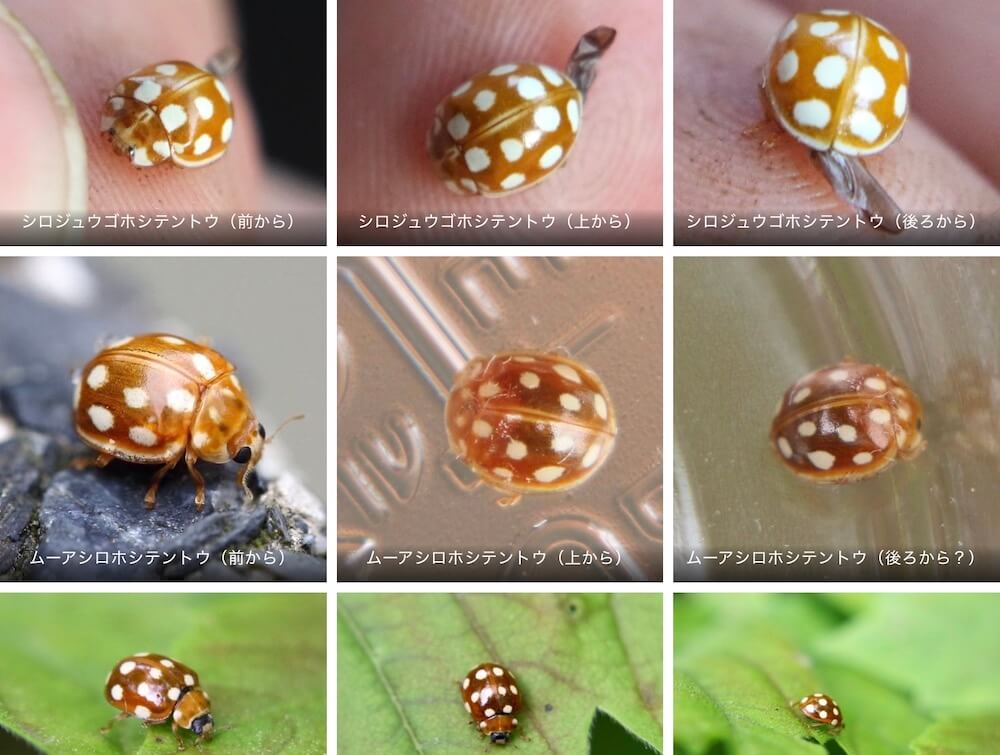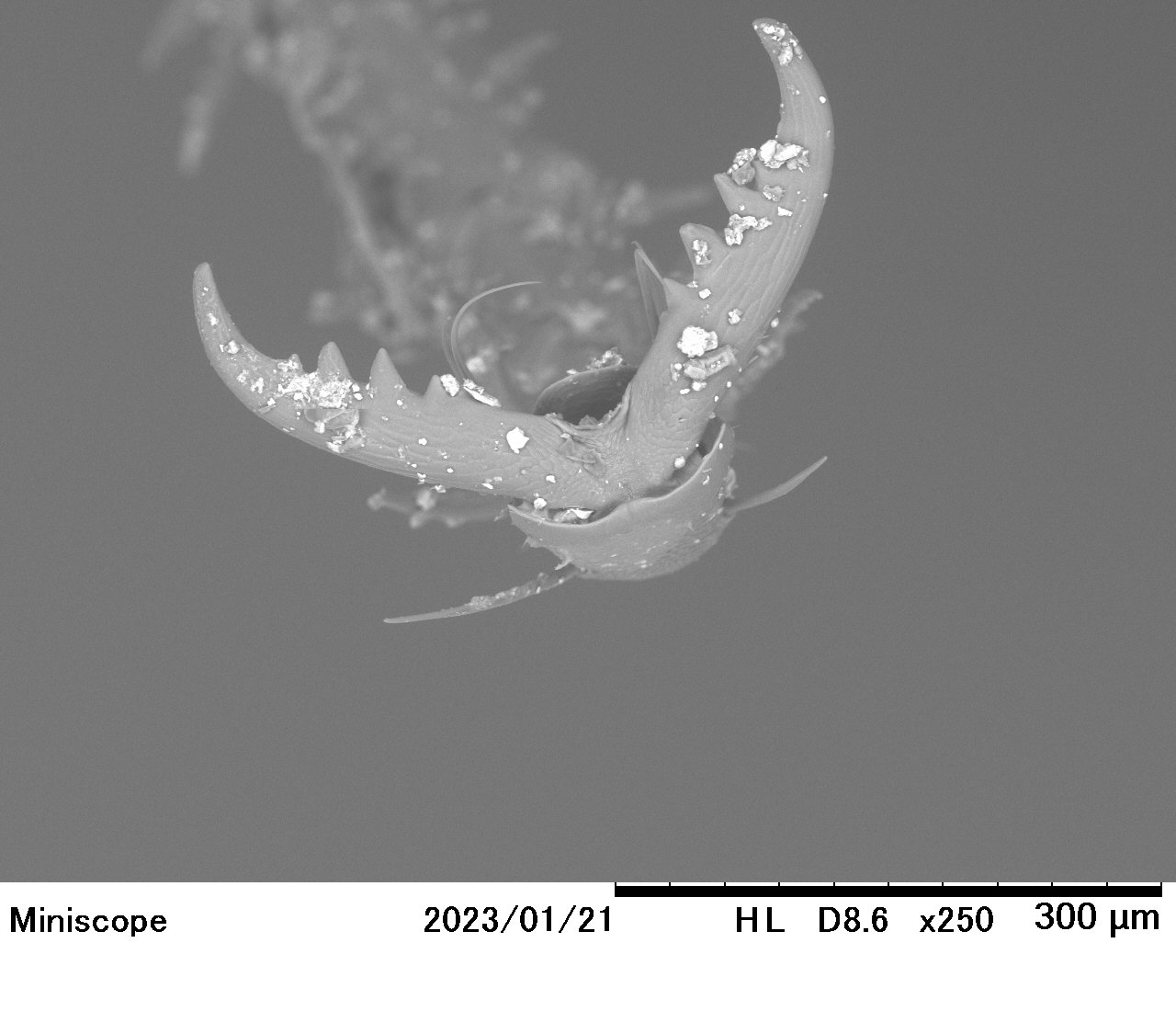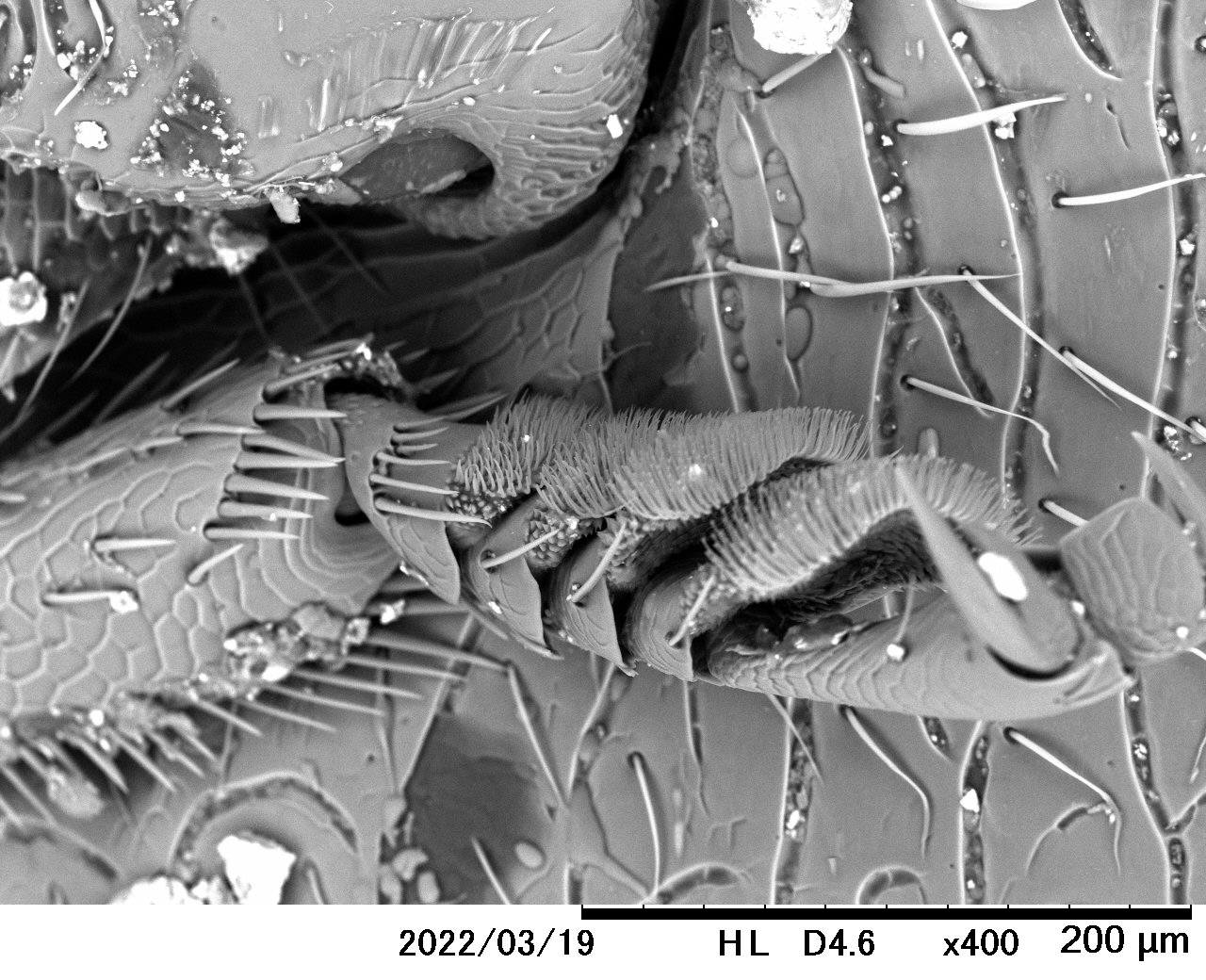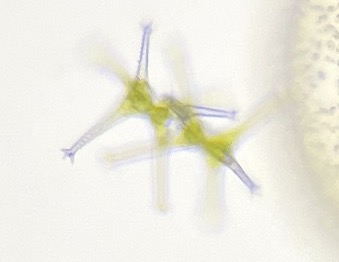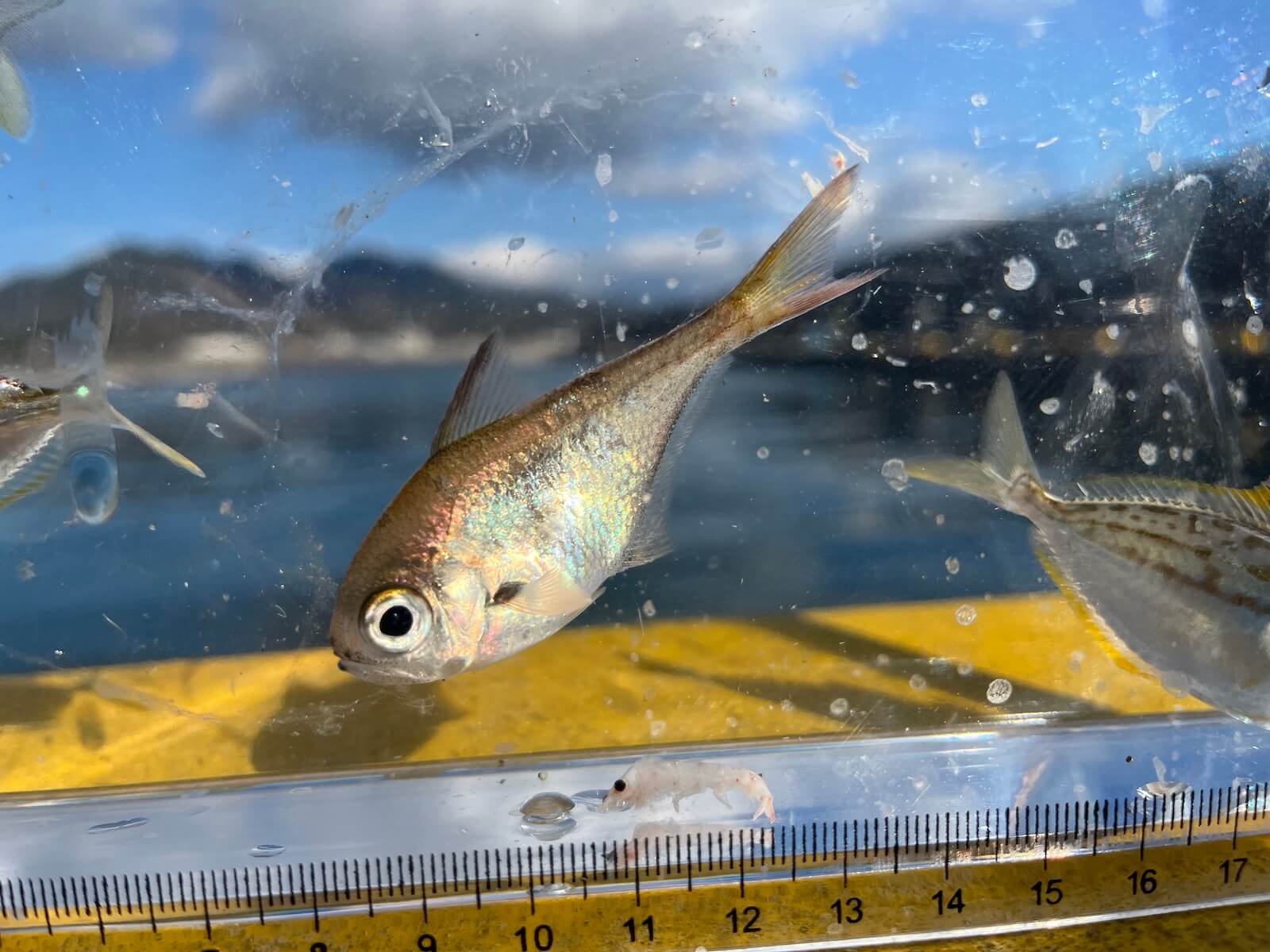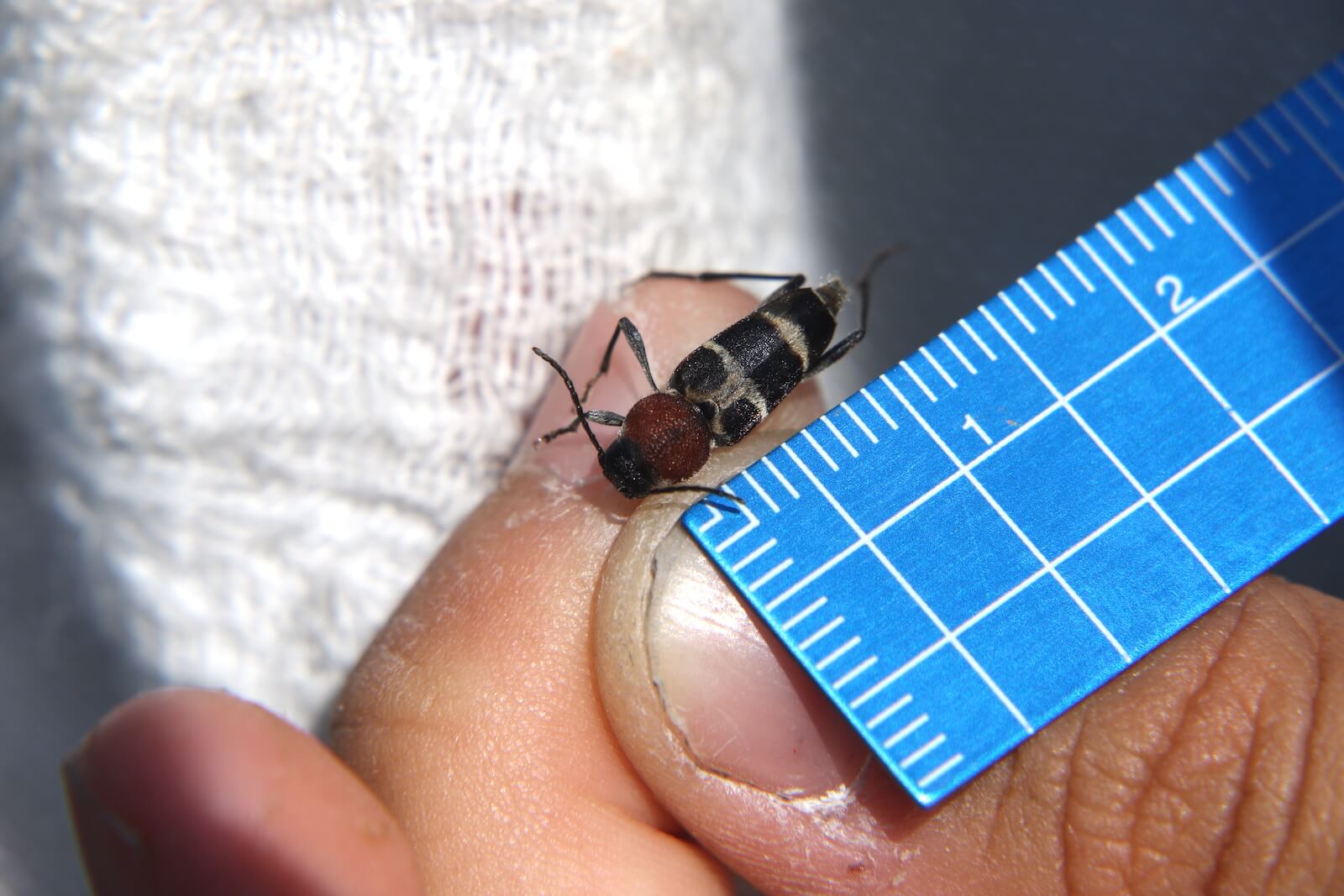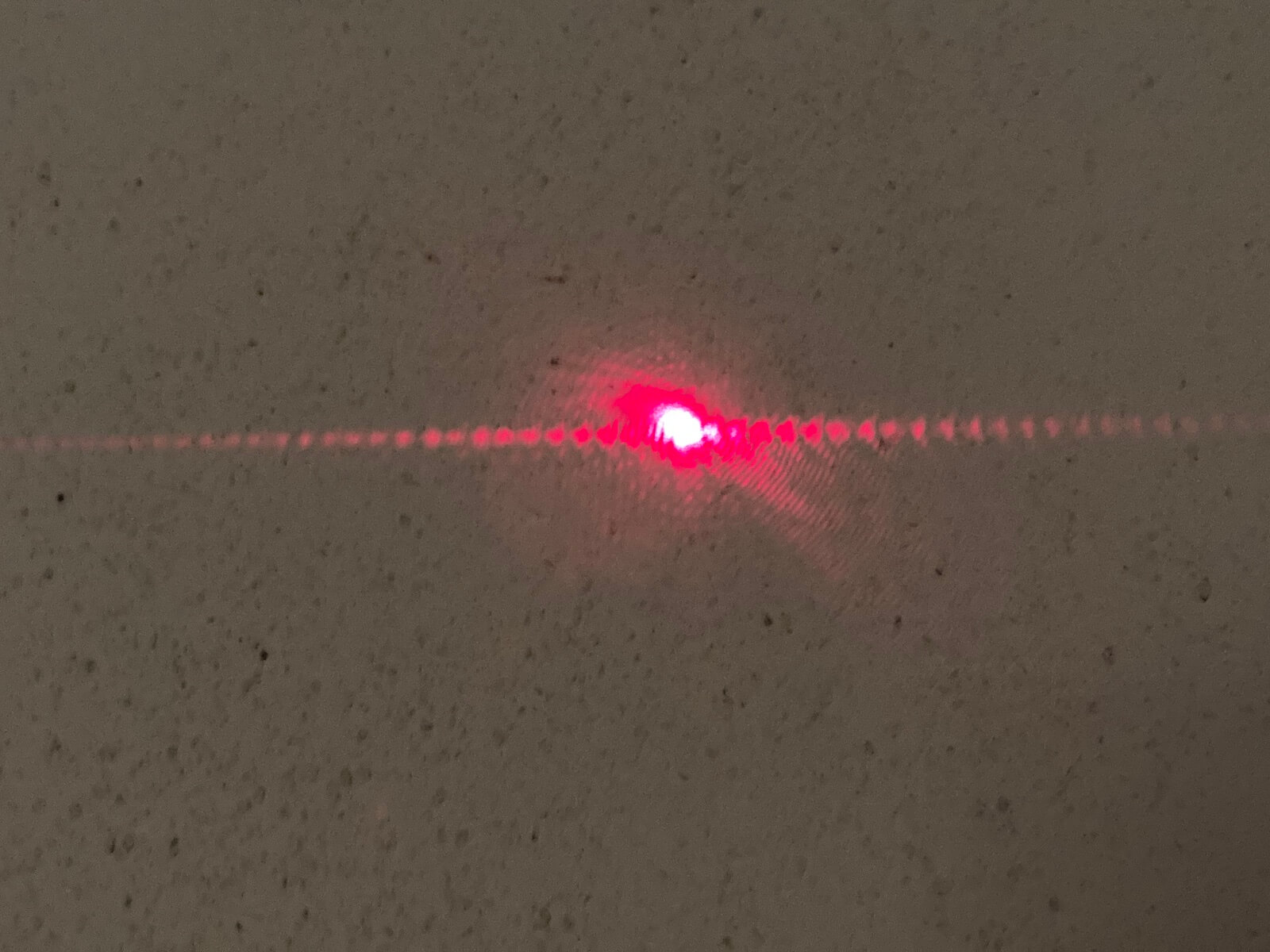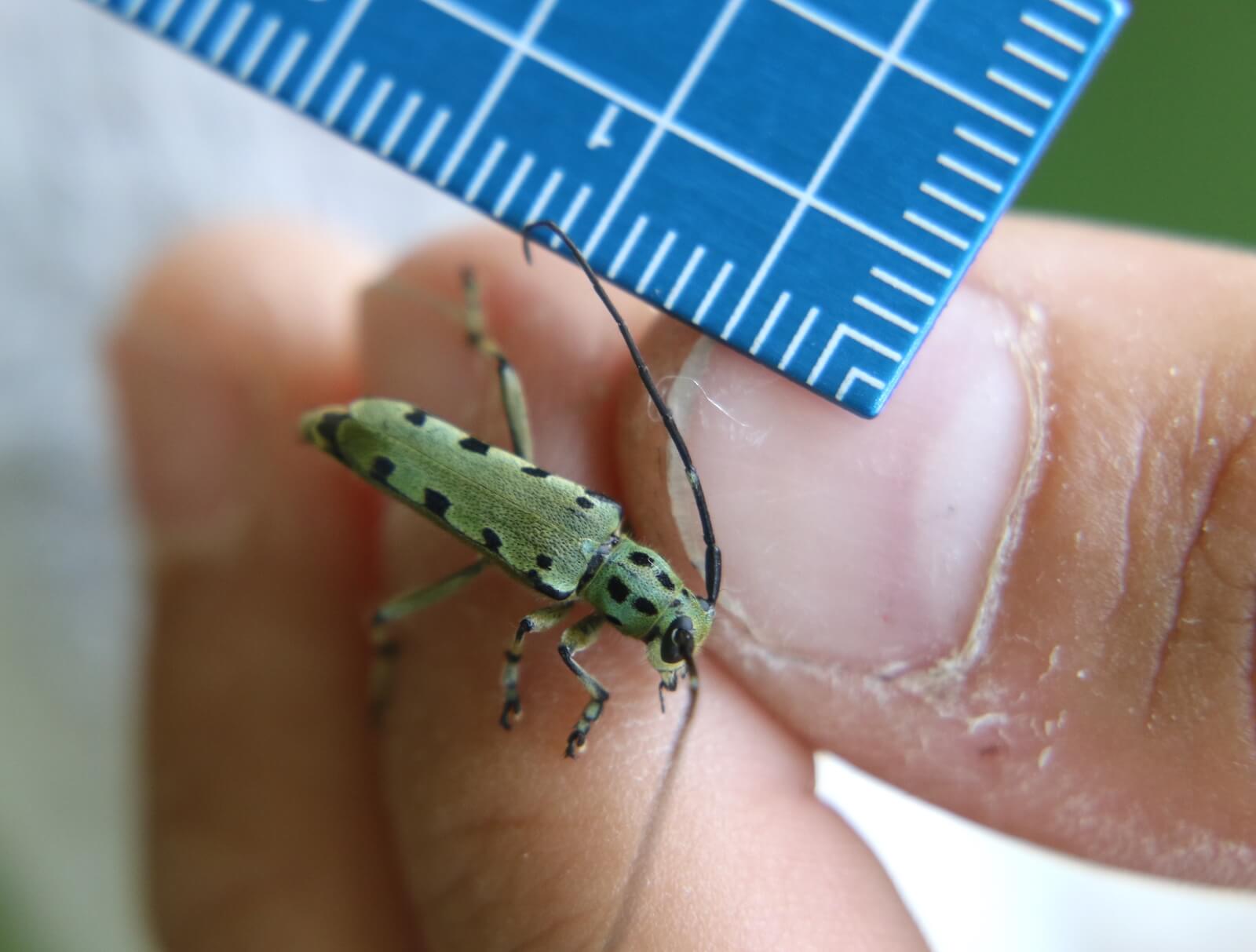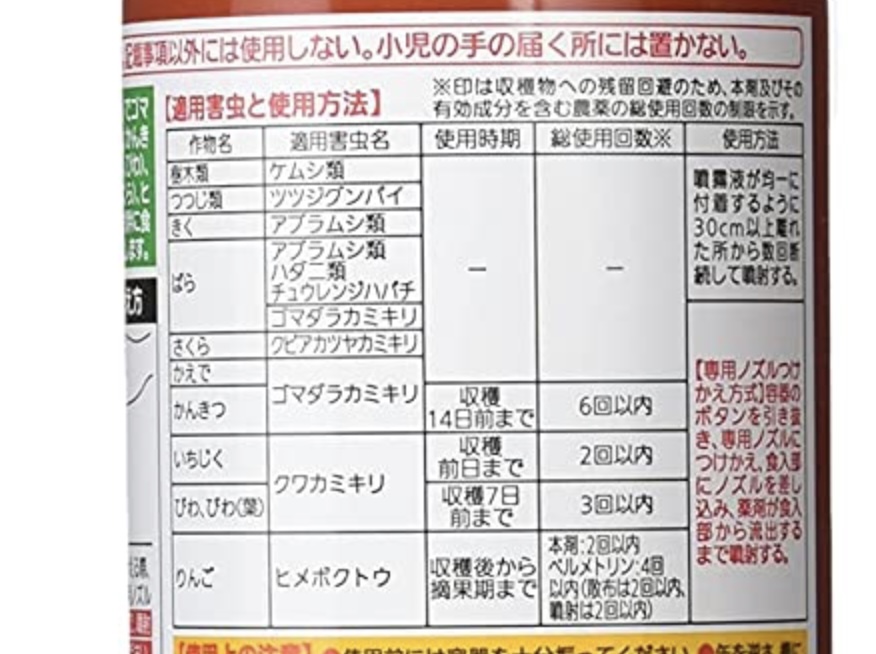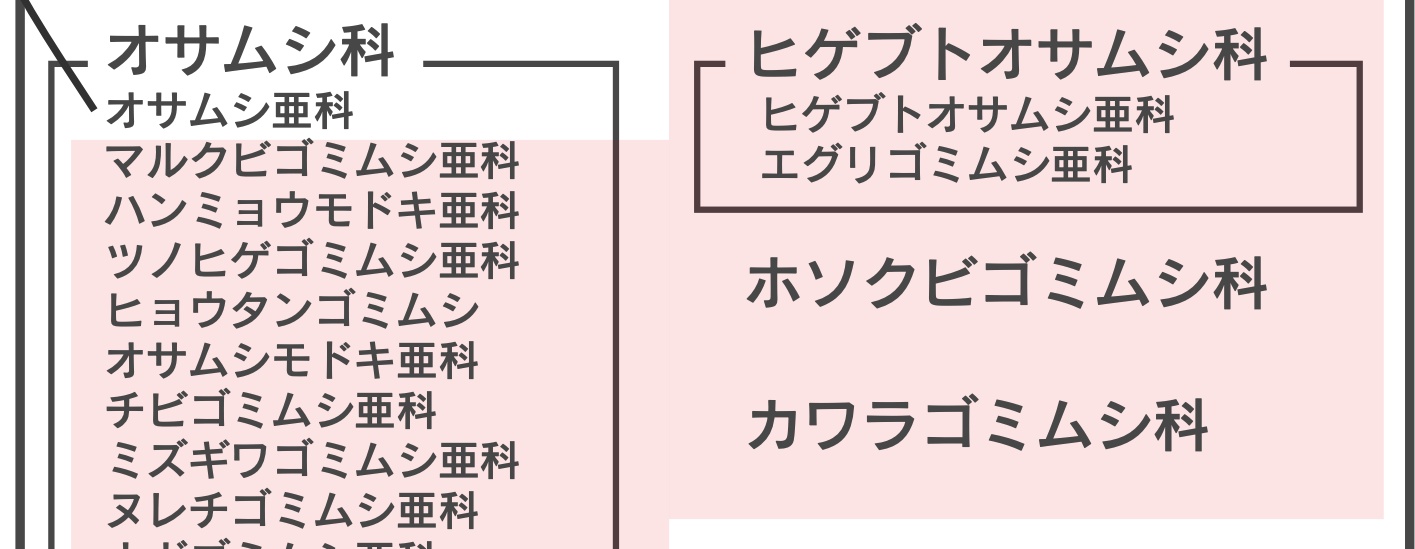-
★★★☆☆ フジヒメハナカミキリは、本州の標高の高い山地 …
-
★★★☆☆ ニセフタオビヒメハナカミキリは、本州の標高の …
-
★★★☆☆ モモグロハナカミキリは、日本の山地に生息する …
-
アカネカミキリはヤマブドウなどにつく小型のカミキリムシ。 …
-
サルナシやヤマブドウの枯れ蔓を歩く小型のカミキリムシ。 …
-
広範な針葉樹をホストとするカミキリムシ。 ヒメマルクビヒ …
-
★★★☆☆ クロルリハナカミキリは、日本の山地に生息する …
-
★★☆☆☆ チャイロヒメコブハナカミキリは、本州でも限 …
-
一本の角(一角、イッカク)が前胸から生えている。 一角は …
-
★★☆☆☆ 四国九州亜種は愛媛、大分で準絶滅危惧種に指定 …
-
★★☆☆☆ 繊細な模様を持ち、本州でも限定されたエリアに …
-
★★☆☆☆ 体長の2倍はあろうかという触覚をもち、褐色と …
-
★★☆☆☆ クモマハナカミキリは標高の高い地域に生息する …
-
ヒメドロムシの中で美麗種と言える。 湧き水を水源とする川 …
-
チョウトンボはトンボ科に属する珍しいトンボ。いつまでも眺 …
-
チャバネクロツツカミキリは広葉樹を宿主とするフトカミキリ …
-
コウヤホソハナカミキリは日本の山地に生息するハナカミキリ …
-
★☆☆☆☆ キイロアラゲカミキリは黄色から黄褐色の毛深い …
-
フタオビミドリトラカミキリは黄緑色の上翅に黒色のふたおび …
-
★☆☆☆☆ アカジマトラカミキリはケヤキの枯れ木や老木に …
-
シナノクロフカミキリはフトカミキリ亜科のカミキリムシ。 …
-
★★☆☆☆ タテジマホソハナカミキリは日本に生息するカミ …
-
★★☆☆☆(絶滅危惧種) ヒメキマダラヒカゲは、チョウ目 …
-
伊豆の戸田港でソウダガツオが簡単に釣れるそうなので、8月 …
-
発見日記(2025年7月 山梨県) スネケブカヒロコバネ …
-
ムナミゾハナカミキリはハナカミキリ亜科のカミキリムシ。1 …
-
ホソツツリンゴカミキリは非常に小さく、楊子のように細長い …
-
★★☆☆☆(絶滅危惧種) キマダラモドキはタテハチョウ科 …
-
★☆☆☆☆ ヘリグロアオカミキリは日本に生息する珍しいカ …
-
ムネグロリンゴカミキリは日本の亜高山帯に生息するリンゴカ …
-
★★★★☆ カマツカはバラ科カマツカ属(ないしカナメモチ …
-
ウラジャノメは日本に生息するジャノメチョウ亜科のチョウ。 …
-
★★☆☆☆ ヤマウツボはシソ目ハマウツボ科ヤマウツボ属の …
-
リンゴカミキリの仲間の見分け方はまず大きさです。20mm …
-
ヘリグロリンゴカミキリは日本に生息するリンゴカミキリの仲 …
-
★★★☆☆ マダラツツキノコムシ(現在はマダラホソツツキ …
-
★★★☆☆ シャガはアヤメ科アヤメ属の多年草。 中国原産 …
-
★★★☆☆ ツルアジサイはアジサイ科アジサイ属の落葉つる …
-
★★★☆☆ イワガラミはアジサイ科イワガラミ属の落葉つる …
-
★★☆☆☆ ミドリヒゲナガは日本に生息するヒゲナガガ科の …
-
クロオビセマルヒラタムシはホソヒラタムシ科に属する甲虫。 …
-
★★☆☆☆ オオカメノキ(別名ムシカリ)は山地の中に疎ら …
-
アカコメツキはコメツキムシ科コメツキ亜科のコメツキムシ。 …
-
★★★☆☆ クロユリはユリ科の多年草。球根植物。 別称、 …
-
★★★★☆ ダンコウバイはクスノキ科クロモジ属の落葉広葉 …
-
★★★★☆ キンシバイはオトギリソウ科オトギリソウ属の半 …
-
★★★★☆ コシアキトンボはトンボ科に属するトンボの一種 …
-
★★★★☆ クロマドボタルはホタル科の一種。 前胸背板に …
-
★★☆☆☆ ニホンアカネはアカネ科アカネ属の多年草。昔、 …
-
★★★★☆ エゴツルクビオトシブミは光沢を帯びた黒色のオ …
-
★★★★☆ オオアオモリヒラタゴミムシは、オサムシ科ゴモ …
-
カタモンオオキノコ(別称、カタモンオオキノコムシ、ニホンカタビロオオキノコムシ)
★★★☆☆ カタモンオオキノコは、オオキノコムシ科に属す …
-
★★☆☆☆ ヤマシャクヤクはボタン科ボタン属の多年草。 …
-
★★☆☆☆ ベニモンチビオオキノコは、オオキノコムシ …
-
★★☆☆☆ タカオトゲアリヅカムシか、その近縁種と推察さ …
-
★★★☆☆ セマダラマグソコガネはコガネムシ科マグ …
-
★★★★☆ カシルリオトシブミはオトシブミ科アシナガオト …
-
日本在来種で庭におすすめの木を樹高ごとにまとめました。 …
-
ニレ科ケヤキ属の日本在来種。公園や街路樹としてよく植えら …
-
イクビモリヒラタゴミムシはモリヒラタゴミムシの一種。 学 …
-
ベニオビヒゲナガは日本に生息するヒゲナガガ科の一種。翅に …
-
学名分類ハモグリガ科大きさ開張分布特徴、生態 山梨県北杜 …
-
クロハネシロヒゲナガは日本に生息するヒゲナガガ科の一種。 …
-
キオビクロヒゲナガノクロは日本に生息するヒゲナガガ科の一 …
-
学名Nemophora bifasciatella分類ヒ …
-
見かける頻度★★☆☆☆学名Oxyporus maculi …
-
★★★★☆ タチツボスミレは日本在来種、身近なスミレの一 …
-
★★★★☆ アカネスミレは山地や低山の尾根辺りや砂地、草 …
-
最近、ブヨに足を刺されて数日痛かったり、脇の下をマダニに …
-
トホシハムシについて 見かける頻度★★★★☆学名Goni …
-
夕焼けのような赤紫色、深山の鮮やかな緑、海のように深い青 …
-
フクラスズメについて 見かける頻度★★★☆☆学名Arct …
-
ハケゲアリノスハネカクシは日本に生息する好蟻性昆虫の一種 …
-
ズグロツヤテントウは山地性の小さなテントウ。 上翅は疎な …
-
タテスジマルヒメドロムシについて 見かける頻度★★★☆☆ …
-
マルヒメツヤドロムシについて 見かける頻度★★★☆☆学名 …
-
樹皮につく地衣類に擬態しているように見える。 見つけた当 …
-
スネアカヒメドロムシについて 見かける頻度★★★☆☆学名 …
-
コマルヒメドロムシについて 見かける頻度★★☆☆☆学名H …
-
アカモンミゾドロムシについて 見かける頻度★★★☆☆学名 …
-
ツブスジドロムシについて 見かける頻度★★★☆☆学名Pa …
-
分類 カミキリムシ科/フトカミキリ亜科 見かける頻度 【 …
-
カワラヨモギは多年草のキク科の在来種。別名シロヨモギ。キ …
-
ケブカヒゲナガは、毛深く触角が長いヒゲナガガ科の一種。 …
-
クスサンは日本の身近な大型のガで、昔はその繭(まゆ)が養 …
-
ムナミゾマルヒメドロムシについて 見かける頻度★★★ …
-
ツヤナガアシドロムシについて 見かける頻度★★★☆☆学名 …
-
ホソハネコバチは羽毛が生えた独創的な形の翅を持つ。 この …
-
ホンシュウセスジダルマガムシについて 見かける頻度★★★ …
-
ミゾツヤドロムシについて 見かける頻度★★★☆☆学名Za …
-
イタドリについて 見かける頻度★★★★★学名Fallop …
-
皇帝ダリア(キダチダリア、コダチダリア)について 見かけ …
-
ナツズイセンについて 見かける頻度★★★☆☆学名Lyco …
-
ヒメナガサビカミキリについて 見かける頻度★★★★☆学名 …
-
日本近海に生息するイシダイ科の魚。大型肉食魚。幼魚、若魚 …
-
見かける頻度 ★★★☆☆ 学名 Allotraeus s …
-
ツヤドロムシについて 見かける頻度★★★☆☆学名Zait …
-
ツヤヒメドロムシについて 見かける頻度★★★☆☆学名He …
-
ガロアケシカミキリについて 見かける頻度★★★☆☆学名E …
-
アトモンマルケシカミキリについて 見かける頻度★★★☆☆ …
-
カッコウメダカカミキリについて 見かける頻度★★★★☆学 …
-
カッコウカミキリについて 見かける頻度★★★☆☆学名Mi …
-
チビハナカミキリについて 見かける頻度★★★★☆学名Gr …
-
タイワンメダカカミキリについて 見かける頻度★★★★☆学 …
-
ヒメアカハナカミキリについて 見かける頻度★★☆☆☆学名 …
-
マツシタヒメハナカミキリについて 見かける頻度★☆☆☆☆ …
-
キベリクロヒメハナカミキリについて 見かける頻度★☆☆☆ …
-
マツシタトラカミキリについて 見かける頻度★★★☆☆学名 …
-
アカイロニセハムシハナカミキリについて 見かける頻度★★ …
-
セスジスズメについて 見かける頻度★★★★☆学名Ther …
-
ウンモンスズメについて 見かける頻度★★★★☆学名Cal …
-
枯葉や枯れ葉に付着する菌類などを食べる、小さな蛾の仲間。 …
-
ヘダイ(平鯛)は銀色がきれいなタイ科の魚。 ヘダイとは? …
-
アジ科の一種。目が大きく、黄色く輝くラインが特徴。 メア …
-
アジ科ムロアジ属の一種。広義にムロアジと呼ばれる場合もあ …
-
ムロアジと言うとき、アジ科の一種「ムロアジ(Decapt …
-
アラキヒメテントウとは? 見かける頻度★★☆☆☆学名Sc …
-
アカマツカサとは? 見かける頻度★★★☆☆学名Myrip …
-
ゴマヒレキントキとは? 見かける頻度★☆☆☆☆学名Het …
-
学名Trachinocephalus trachinus …
-
学名Synodus ulae分類ヒメ目/エソ科/アカエソ …
-
学名Acanthopagrus latus分類スズキ目/ …
-
日本全国に生息するタイ科の魚。日本を代表する高級魚。「魚 …
-
国内で見られるソウダガツオ属の2種のうちの一種。鰹節の原 …
-
マルソウダ:ウロコの上側にある黒斑が背面の黒い部分にくっ …
-
学名Lutjanus decussatus分類スズキ目/ …
-
学名Lutjanus decussatus分類スズキ目/ …
-
学名Plotosus japonicus分類ナマズ目大き …
-
ノシメマダラメイガはノシメコクガとも言われる。また、穀類 …
-
ヒゲナガガ科の一種。上翅の模様はナラやケヤキの虎斑(とら …
-
ゴマフヒゲナガは日本に生息するヒゲナガガ科の一種。 頭部 …
-
フタモンクロテントウはクリの木などにいる2.5mm程度の …
-
学名Platynaspidius maculosus分類 …
-
その属名をとって「グラフィラ」の愛称で親しまれる。ただし …
-
ビャクシンカミキリはヒノキ科の木につくカミキリムシ。上翅 …
-
上翅の点刻は大きくはっきりと観察できる。翅の側縁やお尻先 …
-
学名Pseudocalamobius montanus分 …
-
グラフィラとは?〜その独特のフォルムでカミキリムシファンを魅了♪
カミキリムシ科カミキリ亜科のGlaphyra属は、とうて …
-
茶色と暗褐色のグラデーションの上翅には5対の白い紋がある …
-
磨いて艶を出したような美しい黒色のカミキリムシ。ハナカミ …
-
南方系のカミキリムシ。捕まえて水を与えると良く飲む。 関 …
-
山地、亜高山帯に生息するヒメハナカミキリ、いわゆるピドニ …
-
山地、亜高山帯に生息するヒメハナカミキリ、いわゆるピドニ …
-
最近、ヤツボシハナカミキリの亜種に再分類された。 花粉を …
-
日本に生息するカミキリムシの一種。オオアオカミキリと並び …
-
上翅や前胸に黒と黄色からなる紋を持つカミキリムシ。名前の …
-
ヤマトシロオビトラカミキリ ヤマトシロオビトラカミキリ …
-
日本に生息するカミキリムシの一種。青や緑、金緑色に輝く上 …
-
山地に生息し、カミキリムシファンの間ではその学名(種名) …
-
上翅は退化し短く、後翅が見えている。ヒメバチと似るが、擬 …
-
初春、別の虫を探しに家の近所へ昆虫採集に行ったところ、ち …
-
珍しいカミキリムシ。 その属名をとって「グラフィラ」の愛 …
-
ヘビトンボはヘビトンボ科の大きな虫。この虫が見つかれば、 …
-
一科一属一種の世界的にも特異な虫で、たしかにそのフォルム …
-
翅の外縁にキベリ(黄色い縁取り)があり、その内側に鮮やか …
-
幼虫は乾燥に強く、木工品などを加害する例が報告される。北 …
-
★★★★☆ 山地の草地や林道沿いなどに自生する多年草。紫 …
-
図鑑や昆虫サイトで何度も眺め、いつかは実物をと憧れていた …
-
ホタルブクロはキキョウ科の多年草。背丈は60cmほどで人 …
-
★★★☆☆ フジイバラは生息地が限られる日本の原種ノバラ …
-
まるで蛍光ペンを引いたような明るい緑色が特徴のアブ。山梨 …
-
クロズカタキバゴミムシはオサムシ科ゴモクムシ亜科のゴミム …
-
キノコゴミムシは上翅に2対のオレンジ色の複雑な紋がある美 …
-
日本で見られる野鳥の一覧です。写真をクリックすると詳しく …
-
日本に生息する淡水魚を、生息域が上流から下流の順でご紹介 …
-
公園にいる身近な蝶から絶滅危惧種のチョウまで紹介するWE …
-
ヤマトタマムシが有名なタマムシ科ですが、実は日本には体長 …
-
日本に生息するカエルは48種類。日本の稲作、里山とともに …
-
身近な微生物・プランクトンの種類・図鑑 名前【見かける頻 …
-
鏡のような光沢を持つ上翅の縦スジと、そのスジの間にエメラ …
-
鏡のような光沢を持つ上翅の縦スジ。そのスジの間はビーズが …
-
日本には、200種類近くのトンボが生息しています。ここで …
-
国内で800種以上が報告されるゴミムシには絶滅危惧種も多 …
-
アリの種類・図鑑 身近なアリだが、種類は実に豊富。 &a …
-
日本におよそ360種報告されるコガネムシ科。ここではコガ …
-
日本で見られるクワガタ、カブトムシを写真で紹介しています …
-
絶滅危惧種に指定されている日本の虫、蝶、水生昆虫、甲虫な …
-
アカアシクワガタは脚のつけ根やお腹が赤みがかる日本在来の …
-
クワガタやカブトムシを探しに来たのに、樹液に集まる他の虫 …
-
ミジンコと聞くと種類は1種類だけと思うかもしれませんが、 …
-
日本にいるテントウムシは150種以上。ここではその一部を …
-
日本の蛾の種類・図鑑(見分け・識別・区別) 公園にいる身 …
-
ゴマフカミキリのようないわゆるゴマフ模様ではなく、模様の …
-
日本で身近に見られるハムシを写真で紹介しています。 ★が …
-
ハチの種類 名前【見かける頻度(★が少ないほど珍しい)】 …
-
「飛ぶ宝石」、「宝石蜂」とも呼ばれるセイボウ(青蜂)の図 …
-
日本に800種以上生息すると言われるカミキリムシ。ここで …
-
カタバミ(片喰み)は多年草のありふれた雑草。日本中の公園 …
-
★★★★★ ウツギ(空木、卯木、卯の花)はアジサイ科ウツ …
-
山梨県では山地というよりは亜高山帯の地域で見られる。明か …
-
約5000年前、中国の野生種クワコから改良された種がカイ …
-
カマキリモドキはアミメカゲロウ目/カマキリモドキ科に属す …
-
カミキリムシファンには「グラフィラ」の名で親しまれる。属 …
-
日本のカゲロウの種類・図鑑 日本のゲロウの種類を紹介する …
-
クサカゲロウとしては国内最大。カゲロウと言えば緑色が多い …
-
前翅後縁に蜘蛛の巣が絡まっているような模様が見られる。こ …
-
ヒゲナガゴマフカミキリ(山梨県) 学名Palimna l …
-
ジシバリ(別名、チチグサ、イワニガナジシバリ、センリソウ …
-
長い触角と長い脚、上翅中央やや後方の"程度の大 …
-
平地や低山の広葉樹林で見られる。 目とクチバシの間がはっ …
-
学名Xylotrechus villioni分類カミキリ …
-
学名Epicopeia hainesii分類チョウ目/ア …
-
学名Melligomphus viridicostus分 …
-
ナミハンミョウ〜日本の最も美しい虫のひとつ。別名『ミチシルベ』
学名Cicindela japonica分類オサムシ科/ …
-
学名Bambusicola thoracicus分類キジ …
-
学名Xylotrechus emaciatus分類カミキ …
-
「クサフグ」「コモンフグ」「ショウサイフグ」「マフグ」の違い・区別・見分け方
褐色地に白い点々模様があるフグは堤防釣りなどでよく見かけ …
-
学名Takifugu flavipterus分類フグ目/ …
-
学名Triglidae分類スズキ目、カサゴ目大きさ40c …
-
学名Podiceps auritus分類カイツブリ目/カ …
-
学名Acanthopagrus schlegelii分類 …
-
学名Etrumeus micropus分類ニシン目/ニシ …
-
学名Sardinops melanostictus分類ニ …
-
イワシの区別(マイワシ、カタクチイワシ、ウルメイワシ、カタボシイワシの見分け)
身近なイワシであるマイワシ、カタクチイワシ、ウルメイワシ …
-
学名Sardinella aurita分類ニシン目/ニシ …
-
学名Euprymna morsei分類コウイカ目/ダンゴ …
-
学名Sebastiscus marmoratus分類スズ …
-
マアジとマルアジは似ているが、2つの大きな違いがある。 …
-
学名Decapterus maruadsi分類スズキ目/ …
-
学名Trachurus japonicus分類スズキ目/ …
-
学名Todarodes pacificus分類ツツイカ目 …
-
学名Katsuwonus pelamis分類スズキ目/サ …
-
出世魚の名前一覧表|ブリ・スズキ・ボラ・クロダイ・クロマグロ。ブリなら覚え方は「わかいな笑(わら)」
出世魚(しゅっせうお)とは、幼魚と成魚で名前が違う魚。魚 …
-
学名Todarodes pacificus分類ツツイカ目 …
-
学名Diagramma picta分類スズキ目/イサキ科 …
-
学名Ostorhinchus notatus分類スズキ目 …
-
学名Conger myriaster分類ウナギ目/アナゴ …
-
学名Thalassoma cupido分類スズキ目/ベラ …
-
学名Siganus fuscescens分類スズキ目/ニ …
-
学名Trichiurus lepturus分類スズキ目/ …
-
学名?分類コウチュウ目/大きさ全長0.5mm程度分布本州 …
-
学名Damora sagana (Argynnis sa …
-
学名Callophrys ferrea分類チョウ目/シジ …
-
学名Daimio tethys分類チョウ目/セセリチョウ …
-
学名Erynnis montanus分類チョウ目/セセリ …
-
学名Lampides boeticus分類チョウ目/シジ …
-
学名Somatochlora uchidai分類トンボ目 …
-
学名Elcysma westwoodii分類マダラガ科大 …
-
ネキトンボとショウジョウトンボは似ているが、違いもははっ …
-
学名Crocothemis servilia maria …
-
学名Sympetrum speciosum分類トンボ目/ …
-
学名Aeshna juncea juncea分類トンボ目 …
-
ルリボシヤンマとオオルリボシヤンマは似ているが、2つの区 …
-
学名Gyrinus japonicus分類コウチュウ目/ …
-
学名Girella punctata分類スズキ目/イスズ …
-
学名Physalia physalis分類クダクラゲ目/ …
-
学名Chaetodon auriga分類花クラゲ目大きさ …
-
学名Chaetodon auriga分類スズキ目/チョウ …
-
学名Pentagonica daimiella分類オサム …
-
学名Eretes griseus分類ゲンゴロウ科大きさ1 …
-
アイヌの名の由来は北海道から付けられていると考えられる。 …
-
学名分類コガネムシ科/トラハナムグリ亜科大きさ分布本州で …
-
学名Leptostrangalia hosohana分類 …
-
学名Leptostrangalia hosohana分類 …
-
サペルは、ピドニア、パキタに並び、カミキリムシファンを魅 …
-
学名Eumecocera unicolor分類カミキリム …
-
学名Pidonia maculithorax分類カミキリ …
-
ヒゲナガガ科の一種。異なる色で縁取られたオビ(帯)を持つ …
-
コンオビヒゲナガは日本に生息するヒゲナガガ科の一種。ルビ …
-
学名Monochamus saltuarius分類カミキ …
-
学名Menesia flavotecta分類カミキリムシ …
-
学名Cassida vespertina分類ハムシ科/カ …
-
学名Zeugophora annulata, Pedri …
-
学名Cicindela japana分類オサムシ科/ハン …
-
学名Actenicerus orientalis分類コメ …
-
学名Pectocera fortunei分類コメツキムシ …
-
学名Nebrioporus anchoralis分類コウ …
-
学名Planetes puncticeps分類オサムシ科 …
-
学名Pentagonica angulosa分類オサムシ …
-
学名Epiclytus yokoyamai分類カミキリム …
-
学名Pidonia himehana分類カミキリムシ科ハ …
-
学名Asaperda rufipes分類カミキリムシ科/ …
-
学名Egesina (Niijimaia) bifasc …
-
学名Encyclops olivacea分類カミキリムシ …
-
学名Pseudocalamobius japonicus …
-
学名Leptura dimorpha分類カミキリムシ科/ …
-
学名Rhopaloscelis unifasciatus …
-
学名Pyrrhona laeticolor分類カミキリム …
-
学名Rapala arata分類チョウ目/アゲハチョウ上 …
-
学名Anthocharis scolymus分類チョウ目 …
-
学名Byctiscus fausti分類カオトシブミ科/ …
-
学名Kanekoa azumensis分類カミキリムシ科 …
-
学名Pidonia signifera分類カミキリムシ科 …
-
学名Pidonia sylvicola Kuboki見か …
-
学名Pidonia puziloi分類カミキリムシ科/ハ …
-
学名Pidonia sylvicola Kuboki分類 …
-
分布:本州、四国、九州 大きさ:6〜8mm
-
分布:本州、四国、九州 大きさ:4〜7mm
-
分布:北海道、本州、四国、九州 大きさ:5〜7mm
-
カミキリムシ科/フトカミキリ亜科【見かける頻度】★★☆☆ …
-
体長:10~13㎜ 分布:北海道、本州、四国、九州 カネ …
-
体長:9~16㎜ 分布:本州、四国、九州 カネコメツキ亜科
-
体長:9~12㎜ 分布:本州、九州
-
しろきい系テントウ、似てる4種の見分け方|ムーアシロホシテントウ、シロジュウシホシテントウ、シロジュウゴホシテントウ、シロホシテントウの違い
ムーアシロホシテントウは『胸部の白星』は4つ並ぶが、シロ …
-
オレンジないし赤の地色に黒色のつながった複数の紋があるの …
-
【分類】カミキリムシ科/フトカミキリ亜科/リンゴカミキリ …
-
アシナガオニゾウムシは前脚が長く、身の危険を感じるとその …
-
ゾウムシ科/クモゾウムシ亜科。 黒い地色に黄土色のまだら …
-
4月頃、沢や河川のそばの樹木などで見つかりやすい。アブラ …
-
★★★★☆ 光沢のある黒色で背中に二つのコブがある。後腿 …
-
北海道と本州に分布する美しいチョッキリ。ゾウムシ上科/オ …
-
見かける頻度は★★☆☆☆ 学名はLebia duplex …
-
トガリバアカネトラカミキリの基礎情報 学名Anaglyp …
-
ヒメクロトラカミキリは北海道から沖縄に生息するカミキリ亜 …
-
フタホシテントウは大きさ2〜3mm程度のツヤヒメテントウ …
-
アリガタハネカクシ属のハネカクシ。 本写真はクロサワアリ …
-
北海道〜九州に分布する体長6〜7mmのアトキリゴミムシの …
-
上翅が明るい瑠璃色に輝くハネカクシ科の甲虫。 死ぬとこの …
-
山梨県で見つけた。大きさは2〜3mmほど。 ウスイロコミ …
-
本州〜九州に分布する体長2.5~3mmの微少なヒョウタン …
-
キイロチビゴモクムシ
-
体長11〜12mm程度のゴモクムシ亜科のゴミムシ。 頭部 …
-
大きさ6~6.5mm。ムネミゾマルゴミムシ属の小型ゴミム …
-
暗銅色の鈍い光沢、マットな光沢を帯び、細かな毛に覆われる …
-
※本種は山梨県北杜市で見つかった。ギョウトクコミズギワゴ …
-
暗い緑色、青色の光沢を放ち、足は褐色のゴミムシ。 大きさ …
-
ハギキノコゴミムシは黒色で光具合で緑色の光沢を帯びるゴミ …
-
アカガネオオゴミムシは暗い紫色の金属光沢を持つゴミムシ。 …
-
頭部や胸部が銅緑色の美しいゴミムシ。 足は褐色。 体長2 …
-
上司赤銅色の金属光沢を持つ小型のゴミムシ。 個体や地域に …
-
黒い白鳥。成鳥で全長110〜140cm。カモ目カモ科ハク …
-
体長は10〜25cm。岩手~九州の浅海に生息し、雑食性。 …
-
サッパ(鯯)は汽水域に生息する魚。ニシン目/ニシン科/サ …
-
ヒイラギはスズキ目/ヒイラギ科の海水魚。 釣りでは外道と …
-
カワハギ(皮剥、鮍)は、海水魚。分類はフグ目/カワハギ科 …
-
サソリそっくりのこの虫はカニムシ。サソリの仲間? カニム …
-
クロマルエンマコガネはセンチコガネ科の甲虫。 体長は7~ …
-
オオセンチコガネはサルやイノシシなどの野生動物の糞や腐肉 …
-
ゴロゴロ、グルグルー ゴロゴロ、グルグルーは満足している …
-
ゴミムシの足の先がなにやら二股に分かれてると思って電子顕 …
-
山梨県立科学館で定期的に行っているマイクロズーにて、電子 …
-
スタウラストルム属は緑藻の仲間で植物プランクトン。 琵琶 …
-
ファミリー釣り場や海岸、堤防など、海で見られる魚図鑑です …
-
体長13cm程度、海に住むスズキ目の小魚。堤防や浅い岩礁 …
-
ゾウミジンコはゾウミジンコ科のミジンコ。大きさは0.5m …
-
ボルボックスの見つけ方〜その浅緑(あさみどり)色の繊細な姿に魅了されるファンは多い
ひとたび顕微鏡で見かければ、そのライトグリーンの繊細な姿 …
-
ミツユビカモメは足が短く、一年を通じて黒い小柄なカモメ。 …
-
日本に飛来する代表的なカモメは8種(以下)。特徴や見分け …
-
コカブトは、3cmにも満たない小さなカブトムシの仲間。 …
-
全長60〜68 cmの大型のカモメ。 日本には冬鳥として …
-
全長60cm前後。 その名前からセグロカモメよりも大きい …
-
全長40〜50cmのカモメ。アメリカ、ヨーロッパ、アフリ …
-
全長72cm前後と大型のカモメ。 目の周りはオレンジ味、 …
-
タニグチコブヤハズカミキリは日本固有種。 晩秋、地面に落 …
-
『ユリカモメ』。独特の音の響きとそれにより誘起される不思 …
-
セグロカモメは、全国、とくに西日本で一般的に見られるカモ …
-
ウミネコは全長45~50cm前後、セグロカモメより少し小 …
-
本州から九州にかけ、平野、低地、川沿い、亜高山、高原まで …
-
日本で見られる花を科ごとにご紹介。随時更新。野外での区別 …
-
★★★☆☆ 日本固有種。 一般的なアジサイよりつぼみが大 …
-
ヒメアシナガコガネは体長7〜10mm、北海道、本州、四国 …
-
ビロウドコガネは北海道、本州、四国、九州に分布する小型の …
-
ハルゼミは大きさ23-32mm、本州・四国・九州に分布す …
-
ヒメシロコブゾウムシは本州、四国、九州、沖縄に分布するゾ …
-
オトシブミはオトシブミ科に属する日本国内に23種ほどが生 …
-
★★★☆☆ ゴマダラオトシブミは北海道から九州にかけて分 …
-
ヒメトラハナムグリはコウチュウ目コガネムシ科トラハナムグ …
-
オオトラフハナムグリは黒褐色地にクサビのようにシャープな …
-
ミドリゾウリムシ(Paramecium bursaria …
-
本州、四国、九州に分布する、50〜55mm程度の美しいト …
-
ウスバキトンボは全国に分布し、大群をなして日本列島全体や …
-
北海道、本州、四国、九州に分布するピドニアの一種。 ピド …
-
フサヒゲルリカミキリ〜本州生息種で『種の保存法』に指定されている唯一のカミキリ
フサヒゲルリカミキリは、大きさ15〜17mm程度、フトカ …
-
トゲバカミキリは、大きさ8〜15mmのフトカミキリ亜科の …
-
体長7〜10mmのヒゲの長い小型のゾウムシ。 細い枝を主 …
-
北海道から本州に分布するフトカミキリ亜科のカミキリムシ。 …
-
大きさ6〜9mm程度のカミキリムシ。碁石を配したような柄 …
-
黒色で少し褐色がかっていて光沢がある。オスとメスの違いは …
-
タテジマカミキリはフトカミキリ亜科のカミキリムシ。触角を …
-
ヒバカリは日本在来種の小型のヘビ。昔は毒蛇と思われていた …
-
トンボ科/アカネ属のトンボ。北海道、本州、四国、九州に分 …
-
サカハチチョウは、北海道から沖縄まで分布するチョウ。山地 …
-
大きさ10~14mm程度のカミキリ亜科のカミキリムシ。北 …
-
体長10~27mm。本州、四国、九州に分布するクロカミキ …
-
大きさ5〜9mm程度、ミズナラ、カエデ、クワ、コナラ、オ …
-
大きさ10〜17mmのフトカミキリ亜科のカミキリムシ。北 …
-
ツシマムナコブカミキリ ツシマムナコブカミキリ ツシマム …
-
エゾサビカミキリ エゾサビカミキリ
-
大きさ10〜15mmほどのハナカミキリ亜科のカミキリムシ …
-
本州から九州に分布する、大きさ9〜14mmのハナカミキリ …
-
北海道、本州、四国、九州に分布するハナカミキリ亜科のカミ …
-
ヤマトキモンハナカミキリは北海道から九州にかけて分布する …
-
大きさ9〜14mmのフトカミキリ亜科のカミキリムシ。 北 …
-
ハンノアオカミキリは、大きさ11〜17mm カミキリムシ …
-
本州、四国、九州に分布するピドニアの一種。 ピドニアとは …
-
本州、四国、九州などに分布するピドニアの一種。 ピドニア …
-
カミキリムシ科/ハナカミキリ亜科/ヒメハナカミキリ属(P …
-
カミキリムシファンやカミキリムシ研究者の野望にして宿願、 …
-
体長6~10mm前後、フトカミキリ亜科に属する小さなカミ …
-
北海道、本州、四国、九州に分布するムネアカセンチコガネ科 …
-
体長2.5mm程度、北海道、本州、四国、九州に分布する小 …
-
クビアカヒメテントウは、大きさ2.3〜2.7mm程度の小 …
-
ムネハラアカクロテントウは、大きさ2〜2.5mm程度の小 …
-
アブラゼミは最も一般的なセミのひとつで、公園や庭、道路、 …
-
ミンミンゼミは体長33〜36mmのセミ(翅を含む全長)。 …
-
タマムシ科/ナガタマムシ亜科/ナガタマムシ属に属する、大 …
-
クビアカトラカミキリは小型のトラカミキリ亜科トラカミキリ …
-
ハネビロハナカミキリは体長1.5〜2cm程度のハナカミキ …
-
虫が嫌いな人は多いですが、それはなぜでしょうか? 虫は危 …
-
『宇宙の果ての外側は?』『この天の川銀河に、人類以外の知 …
-
黒い紋が上翅の縁に8つ並ぶことからその名がついた。フトカ …
-
体長6〜10mm程度のフトカミキリ亜科のカミキリムシ。 …
-
コウチュウ目/タマムシ科/ナガタマムシ亜科の微少タマムシ …
-
赤っぽい上翅に白い毛が密に生え、上翅後方には毛の生えてい …
-
里山や雑木林の伐採した枝に5月〜6月になると頻繁に見られ …
-
子どもの間では人気で飼育されることもあれば、果樹や庭木を …
-
分類 コウチュウ目/ガムシ科 大きさ 4~7㎜(成虫の体 …
-
林沿いの休耕田や林の中の水たまり、雨上がりの道路の水たま …
-
広葉樹の枯れ枝などにいるサビカミキリ亜科のカミキリムシ。 …
-
筆でひいたような模様があるカミキリムシ 分類 コウチュウ …
-
広葉樹の枯れた枝やツルにいるフトカミキリ亜科のカミキリム …
-
ラキュのピースのような形をした赤い模様が特徴のアトキリゴ …
-
アトキリゴミムシは樹上や水辺、草地、森林に生息する比較的 …
-
クリの花などに訪花して花粉を食べるアトキリゴミムシの一種 …
-
日本で 70種ほど知られるモリヒラタゴミムシ属の一種。モ …
-
黒色、ないしくすんだ赤色の上翅に黒色の胸部、ハナカミキリ …
-
体長20〜24mmの大型のゴミムシ。 ヒメオサムシに似る …
-
カミキリムシは比較的飼いやすい虫です。 そのカミキリムシ …
-
広範な針葉樹をホストとするカミキリムシ オオマルクビヒラ …
-
セミスジコブヒゲカミキリは針葉樹、広葉樹をホストとする全 …
-
クロズマメゲンゴロウは体長9.5~11.5mmの小型のゲ …
-
ヒメゲンゴロウは体長11〜12.5mmの小型のゲンゴロウ …
-
オオヒメゲンゴロウは体長13〜14mmの小型のゲンゴロウ …
-
ミイデラゴミムシは中型のゴミムシ。高温のガスを噴射するこ …
-
特徴 シイシギゾウムシに似るが、本種はクヌギの葉で見られ …
-
ゲンゴロウ・ガムシ・水生昆虫図鑑 ※ガムシは雑食性・植物 …
-
オトヒメテントウはクリの木などにいる1.5mm程度の微少 …
-
タカハシトゲゾウムシは森林や山地に生息するゾウムシ亜科の …
-
オスは繁殖期に体側が緑や青、オレンジに輝き美しい。 オイ …
-
ニセビロウドカミキリは体長11〜26mmのカミキリムシ。 …
-
トガリシロオビサビカミキリはヤマフジやヌルデ、クリ、オニ …
-
北海道から九州に分布する大きさ10mm前後と小型のカミキ …
-
エノキなど広葉樹の朽ち木などで育つカミキリムシ。大きさは …
-
オシドリ〜世界一美しいカモと称され、アメリカや欧州に移入された
オシドリの分類 カモ目/カモ科/オシドリ属 オシドリの大 …
-
ヒゲナガカミキリは個体数の少ないカミキリムシ。 分類 フ …
-
コムクドリ (小椋鳥)はムクドリと一緒に行動することも多 …
-
川原の石の下や水ぎわの砂地など、水が常に染み出している場 …
-
河原の石の下の砂地に生息する5mmほどの小さなゴミムシ。 …
-
北海道から九州にかけて分布するゴミムシ。 湿った砂地や川 …
-
河原の石の下にいるゴミムシ。昆虫の死骸などを食べる。 大 …
-
黄模様が美しいハネカクシ。 大きさ 16〜20mm程度 …
-
メスグロヒョウモンはオスとメスで翅の模様がまったく異なる …
-
体長 1.5mm 分布 本州〜九州 特徴 体全体がみずみ …
-
ノグチアオゴミムシ ノグチアオゴミムシ ノグチアオゴミム …
-
ムツボシテントウ ムツボシテントウ ケヤキで見つかった小 …
-
オナモミとは?オオオナモミとの違い・見分けも〜通称、ひっつき虫、バカ
いわゆる「バカ」「ひっつき虫」「くっつき虫」として知られ …
-
オナモミ(俗称、ひっつき虫)がくっつく仕組み〜顕微鏡写真で解説
通称、くっつき虫、またはバカ オナモミのトゲの先端がどう …
-
勝手に『かわいい野鳥ランキング』。日本の野鳥はこんなに可 …
-
漂鳥とは渡り(「シベリヤ⇔日本」、「フィリピン⇔日本」) …
-
ナカジロサビカミキリはコナラなどの広葉樹の朽ち木で見られ …
-
オオキベリアオゴミムシやコキベリアオゴミムシと同じく、キ …
-
体色が鮮やかな黄色で美しい。森の中をキビキビと飛ぶ黄色い …
-
森林やその森から続く里山の林などで見られる。昔は茶鶫(チ …
-
https://youtu.be/GPKhd6L5b_8 …
-
コガモのオス(奥)とメス(手間) コガモの群れ コガモの …
-
よく見れば化粧が派手な鵜 翼も黒く縁取られている 集団で …
-
オオルリの青は深くルリビタキの青は淡い オオルリルリビタキ
-
通称、パンダガモ 通称、パンダガモ。ミコアイサのオスの体 …
-
斑紋変異、すなわち背中の模様の変異が激しいカミキリ。 斑 …
-
白鳥(コハクチョウ、オオハクチョウ、コブハクチョウ)の見分け方、区別
日本に生息する野生の白鳥⇒オオハクチョウとコハクチョウ …
-
ハシビロガモは日本には冬に越冬のため渡ってくるマガモ科の …
-
日本に冬にシベリアなどからやってくる野生のハクチョウ。川 …
-
トビ トビ。薄い! ワイヤーにとまるトビ タカの見分け方 …
-
学名Nisaetus nipalensis分類タカ目/タ …
-
カヤクグリは、イワヒバリ科カヤクグリ属の野鳥で、漂鳥。 …
-
https://youtu.be/P8vIJlsaqBo …
-
飛翔姿でのタカの仲間の比較 飛翔中のタカの見分け、違い図解
-
マガモ、マダイ、マダコと同じ感じで真性ヒワ?昔は愛玩用と …
-
狭義のゴミムシ。「ゴミムシ」には『昆虫の1種』を指す場合 …
-
国内に広く分布し、草地、落ち葉の下などに見られる。背中に …
-
分類 オサムシ科/アオゴミムシ亜科/アオゴミムシ属 大き …
-
分類 オサムシ科アトキリゴミムシ亜科 写真 ヤセアトキリ …
-
ゴミムシの定義って?〜その広範で難解な定義を図で簡単にまとめました!
『ゴミムシ』という名称は複雑な広範の甲虫を指しますが、以 …
-
ルイスオオゴミムシに似るが、胸部(前胸部)の、上翅側接続 …
-
クサガメは臭いからクサガメだが、クサシギは臭いからではな …
-
陸に上がるオオバンおしっこ?が輝くオオバン陸に上がるオオバン
-
カンムリカイツブリ カンムリカイツブリ カンムリカイツブ …
-
分類 カイツブリ目/カイツブリ科/カンムリカイツブリ属 …
-
オナガガモは日本では冬鳥の水鳥。マガモやヒドリガモ、キン …
-
『ザ!鉄腕!DASH!!(日本テレビ)』にカミキリムシの …
-
グーグルやYahoo!で「鳥 図鑑」「鳥 種類」と検索す …
-
クロズジュウジアトキリゴミムシ〜専門家でも15年に一回見かける頻度⁉
下の山梨県のレッドリスト(解説?)にも記載されている通り …
-
分類 ウナギ科/ウナギ属 大きさ 成魚:全長1メートルほ …
-
ホトケドジョウは日本固有のドジョウ。他のドジョウより浮き …
-
アオバトは日本の森林に生息する緑色のハト。 分類 ハト目 …
-
明治時代に日本に持ち込まれ、当初こそ園芸用、観賞用として …
-
ヒメアシナガコガネは、果樹の葉やシバを食害することのある …
-
タヒバリは漢字では田雲雀と書き、冬鳥。ヒバリに似ているし …
-
ケリは日本の田んぼにいる留鳥(一年中日本にいる鳥) ケリ …
-
学名Agrilus spinipennis分類タマムシ科 …
-
カタクリハムシカタクリハムシ
-
見かける頻度 ★★★★☆ 大きさ 7.5〜9.5mm 分 …